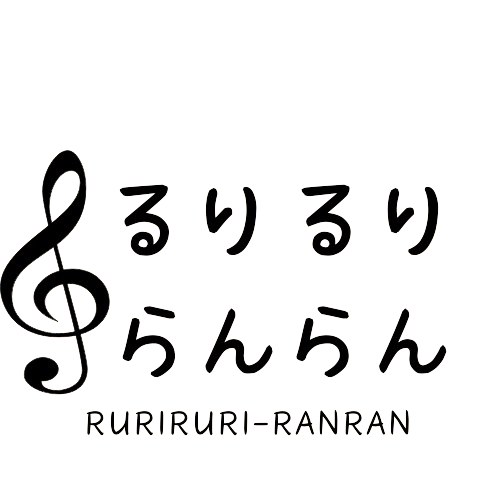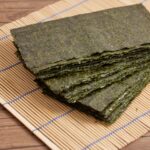「きょうの料理」は
- 四季折々の食材を楽しむ喜び
- 料理を作る喜び
- それを誰かに食べてもらう喜び
を60年以上伝え続けています。
料理家がおいしいレシピを丁寧に説明するので、視聴者が再現しやすい料理番組です。料理初心者から上級者まで、幅広い視聴者が楽しんでいます。
【放送日】2025.4.2(水)
【放送局】NHK
【番組名】きょうの料理
【本放送】Eテレ 月~水曜 21:00-21:24
【再放送】Eテレ 火・水・翌月曜 11:30-11:54 総合 木曜 11:05~11:29
【企画名】ふつうにおいしいもん
【料理人】土井善晴
【料理名】手巻きずし/油揚げの炊いたん
土井先生は
「毎日食べても飽きることのない、持続可能な家庭料理のあり方」を追求しておいでです。
「ふつうにおいしいもん」は、安定の定番料理を、つくりやすいレシピで自分のものにし、おいしくする知恵を授けてくださる人気シリーズであります。
土井節「お料理で苦しむなんて時代遅れやぞ~!」
この回紹介されたレシピ
「油揚げの炊いたん」
油揚げ:6枚
関西の正方形のすし揚げなら12枚
煮干し:6匹
砂糖
醤油
① 鍋にたっぷりの湯を沸かし、沸騰したら油揚げ(6枚)を入れ、落とし蓋をして中火で10分ゆでる。
※ 10分しっかり下ゆでして油抜きし、味をなじみやすくする。
② 落とし蓋で油揚げを押さえるようにして、ゆで汁を捨てる。
③ 鍋に水(2カップ)、煮干し(6匹)を加えて火にかける。
④ 煮立ったら砂糖(大さじ5)を加え、落とし蓋をして弱火で7~8分煮る。
⑤ 醤油(大さじ2)を加え、落とし蓋をして、煮汁が少し残る程度まで30~40分煮る。
【全量】840kcal 塩分5.6g
「いなりずし」
油揚げの炊いたん
すし飯
① すし飯を握って油揚げに詰める。
おすすめ記事
いなり寿司のプチ情報
いなり寿司とは
- いなり寿司は、甘辛く煮た油揚げの中に酢飯を詰めた寿司の一種。
- 手軽に作れて保存性も高く、日本全国で親しまれている。
- 関東と関西で形や味付けが異なり、関東は細長い俵型、関西は三角形が一般的。
由来と歴史
- 稲荷神社の神使(神の使い)であるキツネの好物が油揚げとされ、神前に供えたことが始まりとされる。
- 寿司が庶民の食べ物として普及し、握り寿司の流行とともに発展した。
エピソード
- キツネは油揚げを食べるのか?
実際のキツネは肉食だが、稲荷神社に供えられる油揚げとの結びつきが強く「キツネの大好物」として広まった。 - 東西の違い
関東は俵型で甘めの味付け、関西は三角形で出汁を効かせた薄味。 - 新幹線で販売禁止?
いなり寿司は手軽な駅弁として人気だが、1960年代には「ボロボロこぼれやすく、新幹線の車内を汚す」という理由で一時販売禁止になったことがある。
現在のバリエーション
- 具入り(ゴマ、しいたけ、人参など)
- ちらし風(彩りを加えた華やかなもの)
- 海外では「Tofu Sushi」としてヘルシーフードとして人気
いなり寿司は、シンプルながら奥深く、文化や地域性が詰まった料理であります。
土井善晴さん情報
土井善晴(どい よしはる)さんについて簡単にまとめました。
- 生年月日:1957年2月8日
- 出身地:大阪府
- 職業:料理研究家、フードプロデューサー
- 家族
- 父:料理研究家・土井勝さん
- 母:家庭料理研究家・土井信子さん
- 経歴
- 明星高等学校、芦屋大学教育学部産業教育学科を卒業
- スイスとフランスでフランス料理を学ぶ
- 大阪「味吉兆」で日本料理の修業を積む
- 1992年に「おいしいもの研究所」を設立
- 料理スタイル
- 「一汁一菜」を提唱し、日常の家庭料理の大切さを重視
- ごはんと具だくさん味噌汁を基本とし、日本の伝統的な食事を支える姿勢
- その他
- 十文字学園女子大学特別招聘教授
- 東京大学先端科学技術研究センター客員研究員
- 2022年、文化庁長官表彰
- 映画「土を喰らう十二ヶ月」の料理監修を担当
- 「一汁一菜でよいという提案」など、家庭料理に関する著書多数
おしまいに
最後までお付き合いくださりありがとうございました!